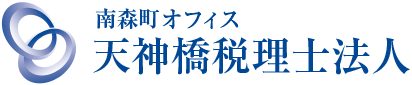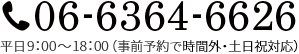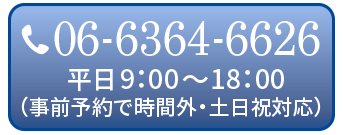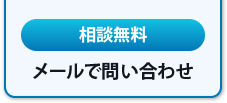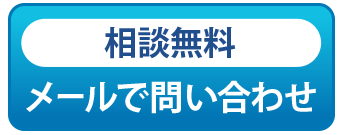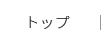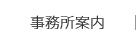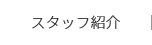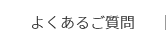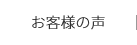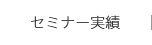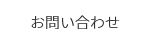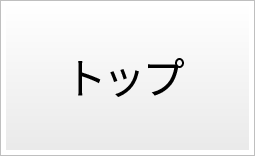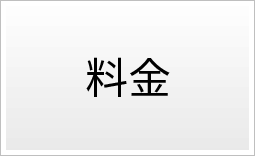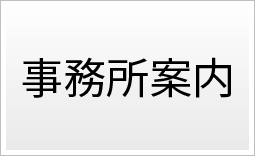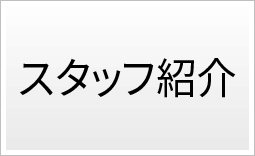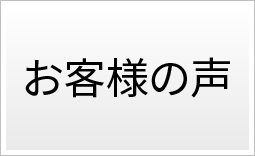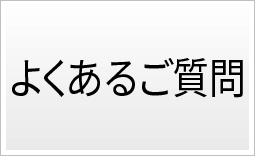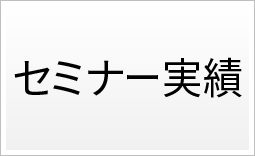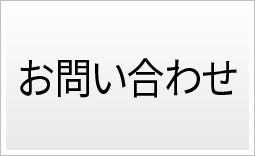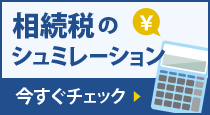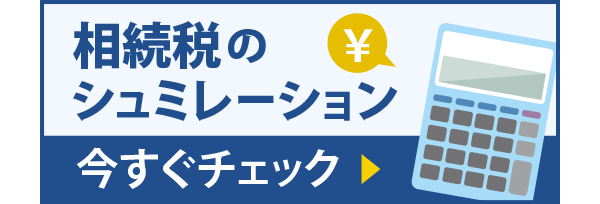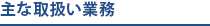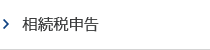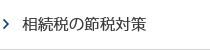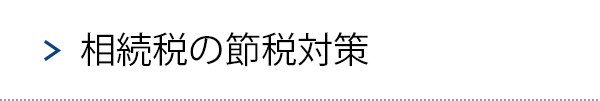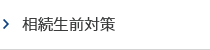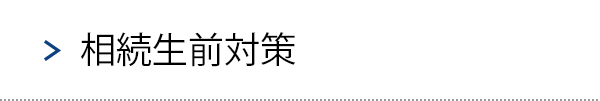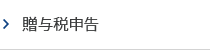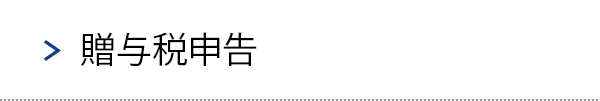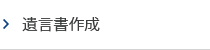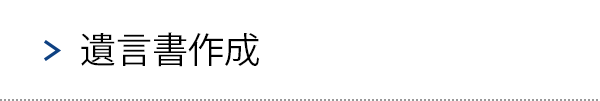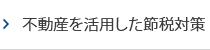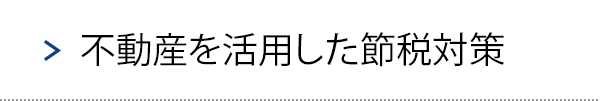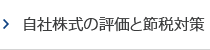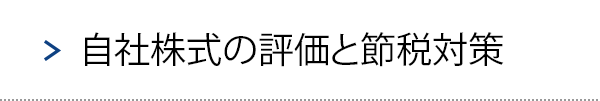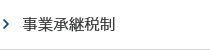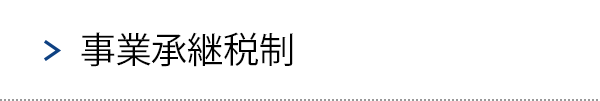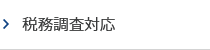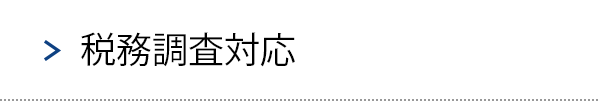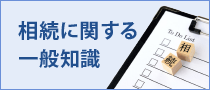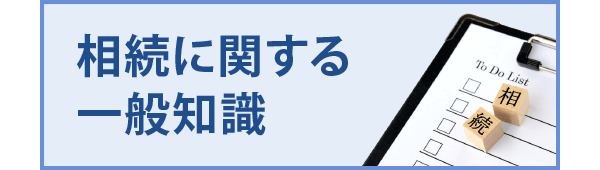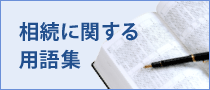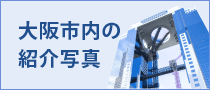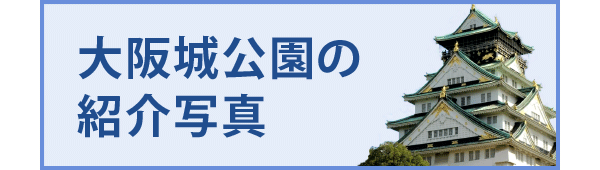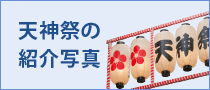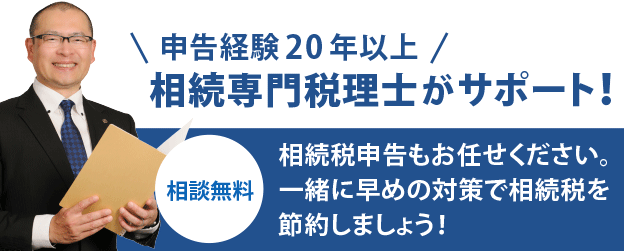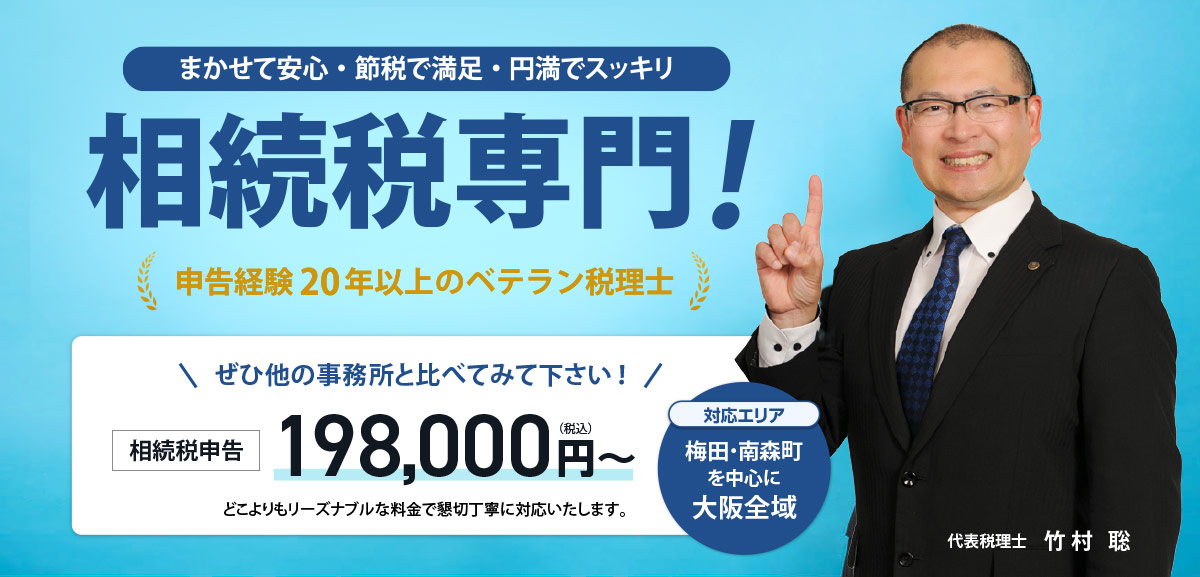
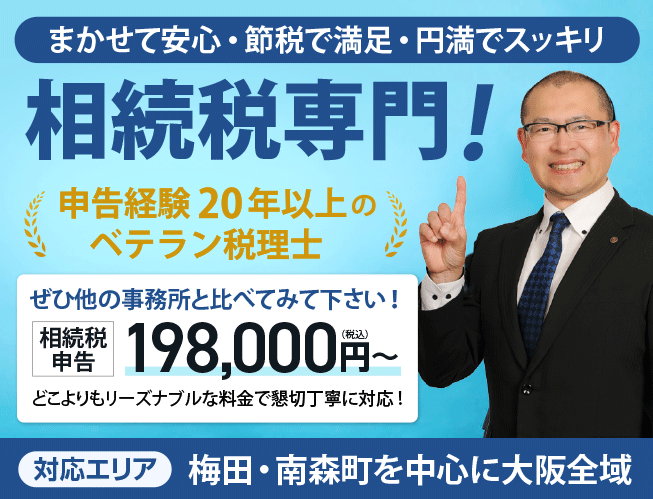
事務所だより
⑧遺言書とは? 遺言書は作成した方が良いですか?
遺言書とは? 遺言書は作成した方が良いですか?
争族トラブルを回避して家族を守るために遺言書を作成しましょう。
「遺言書」と聞くと、「自分にはまだ関係ない」と思われる方も多いかもしれません。
しかし、遺言書は相続をスムーズに進め、家族間のトラブルを防ぐために非常に重要な役割を果たします。
遺言書とは?
遺言書とは、被相続人(亡くなる方)が、自分の財産の分け方や意思を法的に残すための文書のことです。
遺言書があることで、遺産分割の方針を明確にし、家族間の争いを未然に防ぐことができます。
また、遺言書がない場合、法律(民法)に基づいた「法定相続分」に従って遺産が分けられることになりますが、必ずしもその分け方が家族全員の納得する形とは限りません。
遺言書の目的とメリット
1. 遺産分割の方針を明確にする
遺言書によって、誰がどの財産を受け取るかを指定することができます。これにより、家族が遺産分割をめぐって争うリスクを軽減できます。
2. 特定の人に多くの財産を渡せる
法定相続分にとらわれず、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合(たとえば、介護をしてくれた子どもやパートナー)に、その意向を実現できます。
3. 法律では守られない人を守れる
内縁の配偶者や事実婚のパートナーは法定相続人ではありませんが、遺言書で財産を渡すことが可能です。
4. 家族以外の人や団体にも財産を渡せる
親しい友人や支援したい団体に財産を遺すことも、遺言書で実現できます。
5. 相続手続きを簡素化できる
遺言書があれば、遺産分割協議(相続人全員での話し合い)が不要になり、手続きがスムーズに進みます。
6.節税対策につながることも
適切な遺言を作成することで、相続税を軽減する特例(小規模宅地の特例など)を活用しやすくなります。
遺言書の主な種類
遺言書にはいくつかの種類があります。目的や状況に応じて選ぶことが重要です。
1. 自筆証書遺言
自分で手書きで作成する遺言のことです。
•特徴:
手軽に作成できる。
費用がかからない。
法務局で保管制度を利用すれば安全性が高まる。
•注意点:
法的要件を満たさないと無効になる可能性がある。
保管場所に注意しないと紛失や改ざんのリスクがある。
2. 公正証書遺言
公証人が作成し、公証役場で保管する遺言のことです。
•特徴:
公証人が関与するため法的に確実。
紛失や改ざんのリスクがない。
•注意点:
費用がかかる(財産額に応じて変動)。
作成に証人2名が必要。
3. 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう遺言です。
•特徴:
内容を秘密にできる。
•注意点:
法的要件を満たしていないと無効になる。
手続きがやや複雑。
遺言書を作成するタイミング
遺言書はいつ作成しても構いませんが、以下のようなタイミングで作成するのがおすすめです:
•財産が増えたとき(不動産の購入や資産運用の成功など)
•家族構成が変わったとき(結婚、離婚、子どもの誕生など)
•介護や老後の心配が出てきたとき
•相続人間の関係が複雑な場合(再婚家庭や兄弟姉妹が多い場合など)
遺言書作成時の注意点
1.法的要件を守ること 遺言は法的なルールを守らないと無効になる可能性があります。
たとえば、自筆証書遺言ではすべての内容を手書きで書き、日付や署名、押印が必要です。
2.遺留分に配慮する 遺留分とは、相続人(配偶者や子どもなど)が最低限受け取ることが保証されている財産の割合です。遺留分を侵害する内容の遺言は無効になる可能性があります。
3.専門家に相談する 遺言の作成には、弁護士や税理士、公証人などの専門家に相談することで、ミスを防ぎ、より効果的な内容にすることができます。
遺言書がないとどうなる?
遺言書がない場合、遺産は法定相続分に基づいて分けられることになります。
このとき、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)が必要となり、意見の対立が起きることもあります。
遺言があれば、こうしたトラブルを未然に防ぎ、スムーズに相続を進めることができます。
遺言は家族を守る大切な準備
遺言は、あなたの意思を家族に伝え、相続手続きをスムーズに進めるための大切なツールです。
「財産が少ないから不要」と思いがちですが、どの家庭にも必要な場合があります。
家族の未来を守るために、早めに遺言を準備することをおすすめします。
2024-12-26 Tenjin3