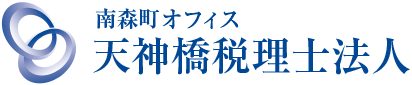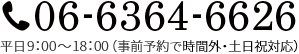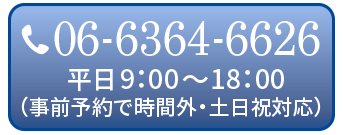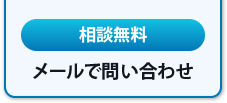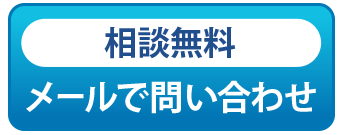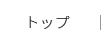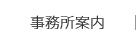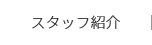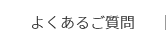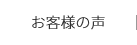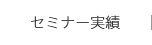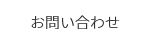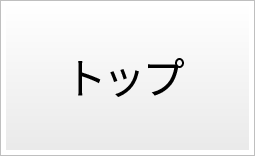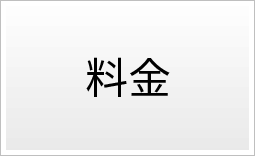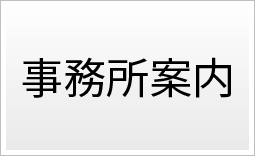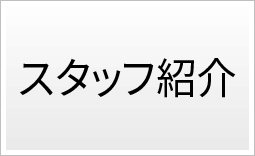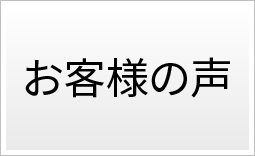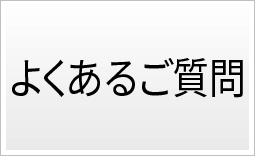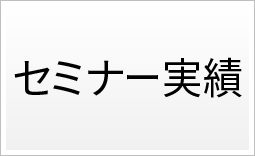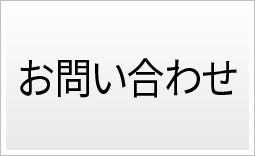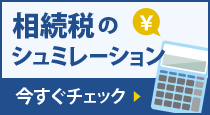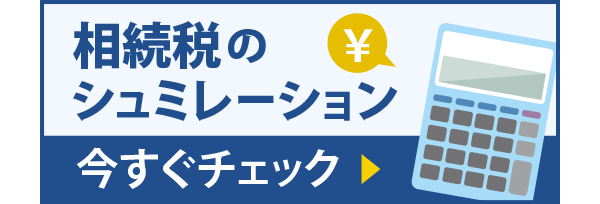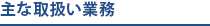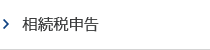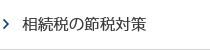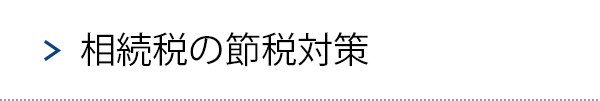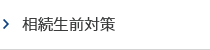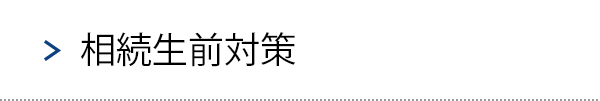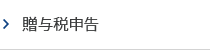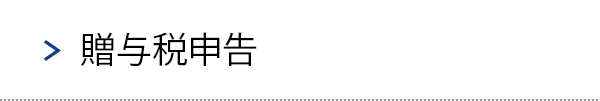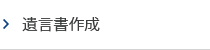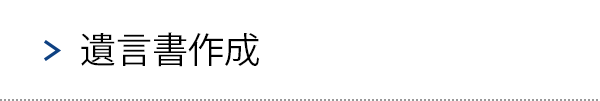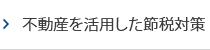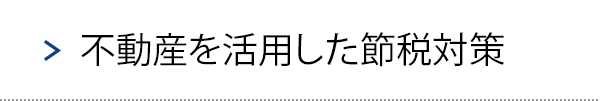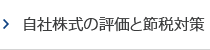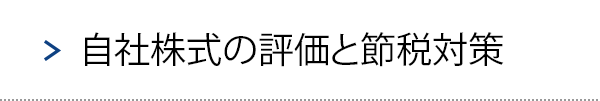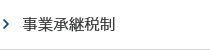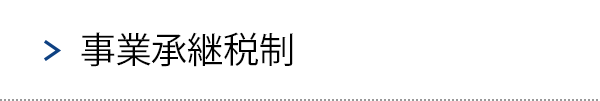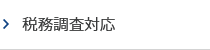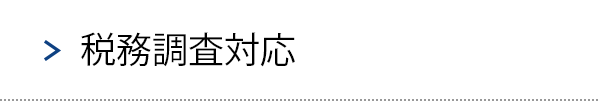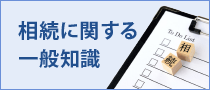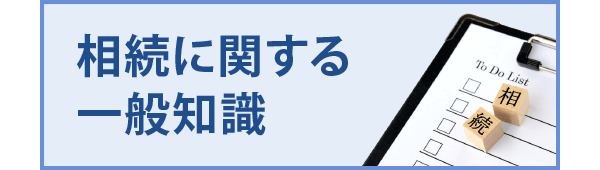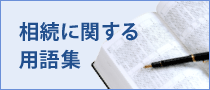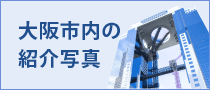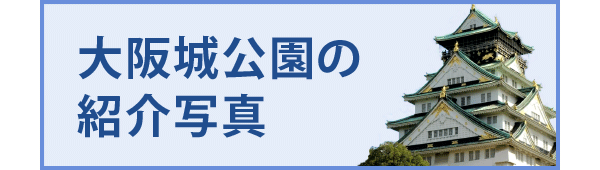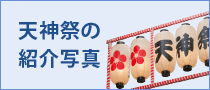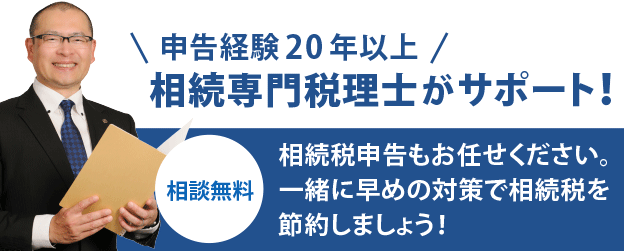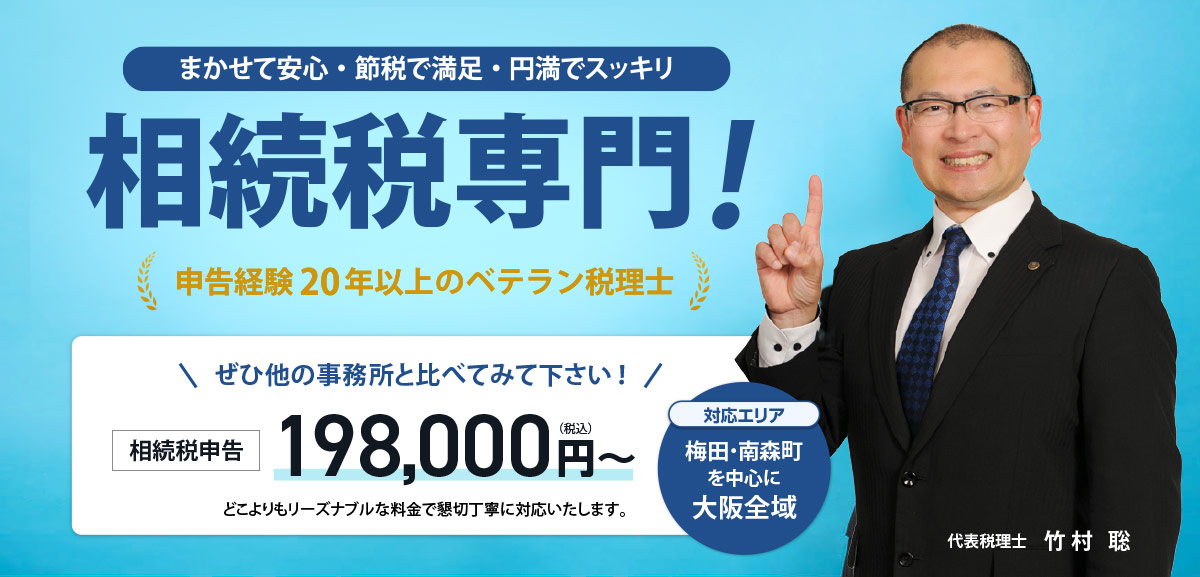
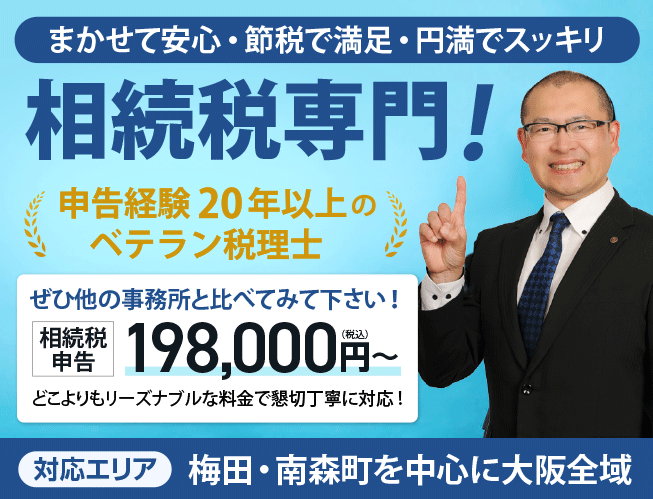
事務所だより
⑤法定相続人の持分とは?
法定相続人の持分とは?
法定相続人の持分とは、法律で定められた「遺産をどれくらいの割合で分けるか」という目安のことです。
持分は法定相続人の関係性や家族構成によって変わり、遺産分割の際の基準となります。
持分の決まり方
法定相続人の持分は、次のような家族構成によって決まります。
1. 配偶者と子どもがいる場合
•配偶者:1/2
•子ども全員で1/2を均等に分ける
たとえば、配偶者と子ども2人がいる場合:
•配偶者:1/2
•子ども1人あたり:1/4
2. 配偶者と親(直系尊属)がいる場合(子どもがいない場合)
•配偶者:2/3
•親全員で1/3を均等に分ける
たとえば、配偶者と両親がいる場合:
•配偶者:2/3
•父:1/6
•母:1/6
3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子どもも親もいない場合)
•配偶者:3/4
•兄弟姉妹全員で1/4を均等に分ける
たとえば、配偶者と兄弟姉妹2人がいる場合:
•配偶者:3/4
•兄弟姉妹1人あたり:1/8
4. 配偶者のみがいる場合
•配偶者が全財産を相続します(持分:1/1)。
5. 子どものみがいる場合(配偶者がいない場合)
•子ども全員で均等に分けます。
法定相続分と遺産分割の違い
法定相続分は、あくまで「法律上の基準」です。
実際の遺産分割では、法定相続分に従う必要はなく、相続人全員が合意すれば自由に分け方を決められます。
例えば:
•配偶者が生活費に困っている場合、子どもたちが配偶者の取り分を多くすることに同意するケース
•特定の相続人が実家の土地を相続し、他の相続人が現金を多く受け取るケース
このような場合は、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成することで合意内容を確定します。
ただし、遺言書がある場合
遺言書で遺産の分け方が指定されている場合、法定相続分ではなく遺言の内容が優先されます。
この場合でも、遺留分として法定相続持ち分の半分は請求できる権利があります。
2024-12-21 Tenjin3